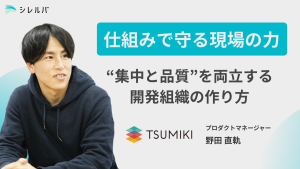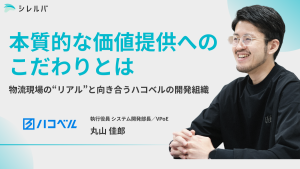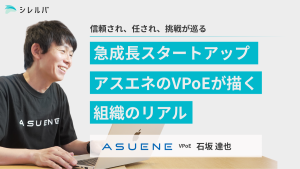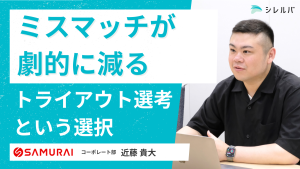セーフィー株式会社
VPoE
開発本部 エンジニアリングオフィス 室長
武田 智一
セーフィー株式会社 VPoE。2023年1月入社。前職のビズリーチでは400名規模のエンジニア組織の立ち上げと組織開発を担当。複数社を経験し、2018年以降は一貫してエンジニア組織づくりに携わる。
クラウド録画型の映像プラットフォーム「Safie(セーフィー)」を展開するセーフィー社。映像を“社会の目”として活用し、さまざまな業界の課題解決に挑戦しています。そんな同社では、プロダクトと同じように、スケーラブルな組織運営が求められていました。
特定の個人の能力だけに依存せず、誰がやっても機能する運営体制をどう築くか。その鍵を握るのが、同社が独自に設けている横断組織「エンジニアリングオフィス」です。設立の背景から実際の取り組み、現場との関わり方まで、VPoEの武田さんにお話を伺いました。
映像の力で社会課題を解く。「Safie」が描く未来のプラットフォーム
まずはセーフィー社の事業内容と、その特徴的な点について教えてください。
セーフィーは「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、クラウド録画型の映像プラットフォーム「Safie」を展開しています。カメラを通して取得された映像を、クラウドで管理・分析することで、防犯や記録を超えた活用ができるのが最大の特徴です。
具体的には、建設現場での進捗確認や、スーパーでの値引きタイミングの最適化など、さまざまな業務領域において「映像×AI」による業務効率化や意思決定支援を行っています。
私たちはハードウェアメーカーではありません。メーカーとは異なり、“カメラを売る”のではなく、“映像を通じた価値”を提供することを目的にしています。実際にセーフィ―の映像プラットフォームはすでに30万台以上のカメラと接続されており、国内外に利用が広がっています。

組織の複雑性とスケールに立ち向かう。エンジニアリングオフィス設立の背景
現在は、どのような組織構成で開発が行われているのでしょうか?
開発本部の下に11個の部門があり、インフラ、アプリ、モバイル、AI、デバイス、データ活用、ソリューションなど、機能別に編成されています。セーフィーの特徴は、ソフトウェアとハードウェアの両方を扱っている点にあり、そこが組織づくりの難しさでもあります。
たとえば、デバイス開発部はカメラファームウェアやセンサー連携などを担い、他部門とのインターフェースも非常に多岐にわたります。一方で、プロジェクトごとに部門横断でチームが編成されるので、縦割りと横断のバランスが非常に重要になります。
組織運営における課題を、どのように捉えていたのでしょうか?
複雑な開発体制を持続可能にするには、“個人の経験や勘だけに頼らない”構造的な仕組みが必要になる過渡期でした。しかし当時はまだベンチャーマインドがあり、マネージャーの裁量に委ねられた運営や、暗黙知ベースの評価・育成が行われていました。
私がセーフィーに入社した2023年当初、すでに開発部門は100名規模に近づいており、役割や運営体制の整備はまだ追いついていない状態でした。意思決定や育成など、現場の“経験と勘”に頼る部分が多く、継続的に組織を成長させるための「構造的な支え」が不足していたのです。どこかで限界がくる。スケールしない。その危機感を、現場のマネージャーたちとも共有していました。
そこで登場したのが「エンジニアリングオフィス」なのですね。
はい。課題の根本を解決するべく立ち上がったのが「エンジニアリングオフィス」です。2022年末に構想が始まり、2023年に私が正式に参画しました。
再現性ある組織をつくる。“浸透仕組みの設計”に挑むエンジニアリングオフィス
エンジニアリングオフィスとは、具体的にどのような役割を担う組織ですか?
エンジニアリングオフィスは、セーフィーの開発組織における“仕組みの設計と浸透”を担う専門組織です。エンジニアの採用・育成・評価・オンボーディング・キャリア設計などを「個別対応」ではなく、「全体設計」として捉え直し、再現性のある仕組みに落とし込むことを目指しています。
実際にどのような取り組みをしてきたのでしょうか?
最初に手をつけたのは「評価制度の再構築」でした。これまでは個々人の感覚に依存した評価が多く、チームや個人の役割に応じた期待値が明確ではありませんでした。全員の顔がわかる数十人規模の組織ならそれでも良いかもしれませんが、すでに100名規模となり評価の軸が欲しいという声も上がっていました。そこで、元々重視していたカルチャー体現はそのままに、エンジニア特有のスキルや行動・成果・影響力の観点からランクテーブルを策定し、期待される役割や成長ステップを言語化しました。
ただ、それだけでは制度は現場に浸透しません。「なぜ導入するのか」「どう活用すべきか」を伝えるため、背景説明・運用マニュアル・Q&A・ワークショップ資料までを丁寧に整備しました。制度を定着させるには“説明責任”も仕組みの一部であるというのが私たちの考えです。今も現場の声をもとにアップデートを重ね、「現場で使える仕組み」への進化を続けています。

仕組みづくりにおいて、大切にしているスタンスはありますか?
「完璧なものを作ってから導入する」というより、「8割くらいの完成度でもまずやってみる」ことを大事にしています。特に組織づくりにおいては、“運用されてこそ意味がある”ので、実際に現場に出してフィードバックをもらいながら改善していくスピード感を重視しています。
評価制度以外に、印象に残っている施策はありますか?
評価制度と併せて取り組んだのが、開発本部会の見直しです。当時開発本部全員を集めた月に一度の全体会議が行われていました。組織開発において情報設計はとても重要です。そこで、この開発本部全体の会議から改善して、情報格差をできるだけなくそうと考えました。
具体的には会議自体の役割の再定義からアジェンダの再設定を実施し、タイムリーな話題の共有をおこなえる運用体制を作りました。結果として、満足度が90点を超えるほど活用できている会とすることができています。
※詳細はセーフィーテックブログでも公開しています。
https://engineers.safie.link/entry/change-organizational-meetings
現場との距離感——「何してるの?」から「関心がある」へ
エンジニアリングオフィスに対する現場の反応はいかがですか?
立ち上げ当初は、正直「何してるの?」という声も多かったです。私たちはプロダクトを直接つくっていないし、現場で開発をしているわけでもない。いわば“黒子”のような存在です。
ただ、最近では「面談資料が使いやすかった」「評価制度が納得しやすくなった」といった声が増えてきましたし、率直な指摘やフィードバックが届くようになってきたのも、前進だと捉えています。また、ネガティブな意見も正直あります。ただそういった意見が出ること自体、無関心ではなくなったということですし、関心があるからこその期待だと感じています。
現場とのコミュニケーションで意識していることはありますか?
「支援する側が正しい」というスタンスではなく、今までやってきたことに感謝し、“共に考える伴走者”であることを意識しています。たとえば「こういう課題があるよね」といった気づきを提示する際にも、一緒に壁打ちしたり、現場に任せたりと、相手に合わせた関わり方をしています。
再現性ある組織の鍵は、“未来からの逆算”
お話を聞いていると、かなり先を見据えた取り組みをされていると感じます。
その通りで、2024〜2026年の3か年で“どういう組織をつくるか”という戦略も考えています。これには、採用、オンボーディング、育成、評価、キャリア開発、インナーブランディング、発信などすべてを一続きのストーリーとして落とし込んでいます。
たとえば、ポテンシャル層を積極的に採用したいと考えるなら、それを支えるオンボーディング制度が欠かせません。そこから逆算して評価基準も変え、配属や育成体制も見直す。すべてが一連のストーリーになっていなければ、施策は“点”にしかなりません。
戦略を描くだけでなく、どう“続けるか”も重要ですよね。
まさにそこが一番難しいポイントです。私自身、「最初の一歩」は得意でも、「継続して根づかせる」部分はすごく意識しています。組織が変化し続ける以上、制度も仕組みもアップデートが必要です。だからこそ、現場との対話を絶やさずに、柔軟に調整していけることが大切だと思っています。

組織の未来をどう描くか──VPoEとしての視座
VPoEとして、これからどんな組織をつくっていきたいと考えていますか?
大切にしたいのは、「誰かひとりの力で成り立つ組織」ではなく、「チームとして成果を出せる組織」です。そのためには、評価や育成の仕組みだけでなく、日々のコミュニケーションや心理的安全性といった“見えにくい部分”にも向き合う必要があります。
また組織は「人」の集まりであり、実行するのも「人」です。どんな立派な計画やプロセス、仕組みや制度があったとしても、実行するメンバーが共感しワクワクしたものでなければ継続できません。絵に描いた餅にならないように、「人」の成長にもコミットして組織づくりをしていきたいと考えています。
「チームとして成果を出せる組織」の実現のために、どのような取り組みをされていくのでしょうか?
そのためにも今後は、より「中長期を見越した組織戦略の策定と実行」に注力したいと考えています。中長期の組織戦略やビジョンは、組織が向かうべきゴールであり、仕組みを使いこなす“かなめ”です。判断に迷ったときに頼れる材料があるかどうかが動き方を左右すると思います。最高なプロダクトやサービスを提供し続けるための組織とは何かを考え続けていきたいです。
もう一つは、組織が“自走できる状態”を目指すこと。仕組みはあくまで道具にすぎません。そして使うのは「人」です。その「人」の行動変容を促せるような仕組みが常に最新化されている状態を作りたいです。
たとえば、1on1のテンプレートや評価の基準表などがあれば「何をどう話すか」「どんな振る舞いが期待されるか」が明確になり、より中身の話に注力できます。仕組みがあることで、誰もが判断しやすくなり、迷わず動ける。
私は、そういう組織が強くなっていくと思っています。
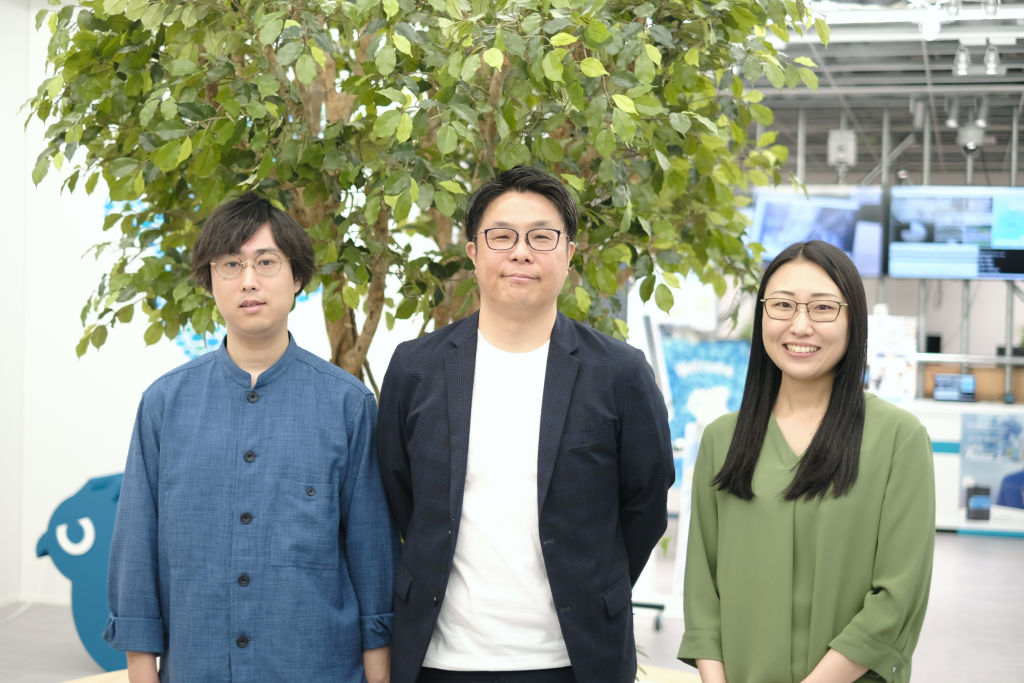
エンジニアリングオフィスメンバー(左:髙木さん 中央:武田さん 右:山崎さん)
編集後記
セーフィー社の取り組みで印象的だったのは、「制度をつくる」ことよりも、「どう現場で活かすか」に重きを置いている点でした。評価制度や1on1支援の整備においても、「どうすればメンバーが前向きに動けるか」「現場で本当に機能するものとは何か」を考え抜く姿勢が一貫していました。
もちろん、仕組み自体に万能な解はありません。けれど、明文化されたルールや型があることで、人は迷わず動ける。判断の負荷が減り、対話に集中できる。だからこそ、組織は次の一歩を踏み出せるのだと感じました。
制度や仕掛けは、現場の力を引き出すための”土台”になり得る——セーフィー社の取り組みは、組織づくりにおけるそんな前提を、あらためて教えてくれるものでした。