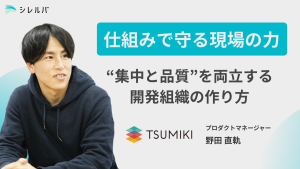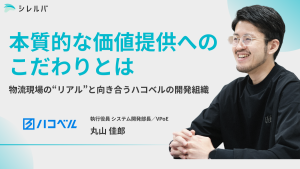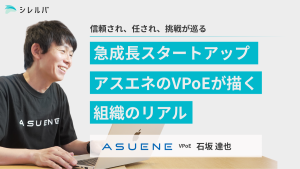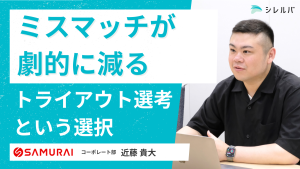株式会社RemitAid
CTO
岩崎 喬
新卒で独立系SIerに入社し、大手企業向けの業務改革やシステム導入支援に従事。その後スタートアップに転職し、エンジニアリングマネージャーやプロダクト責任者を歴任。2022年、RemitAidにCTOとして参画。バックエンドからプロダクト設計、チームマネジメントまで幅広く担いながら、スケール可能な開発体制とカルチャーづくりを牽引している。
創業3年目にして、クロスボーダー決済領域で躍進を続けるFinTech スタートアップのRemitAid社。正社員エンジニア3名というコンパクトな体制ながら、複数プロダクトを展開し、スケーラブルな開発と組織運営を実現しています。
本記事では、CTO 岩崎さんへのインタビューを通じて、RemitAid社がどのようにして少数精鋭でもスケール可能な開発体制と強い組織文化を築いているのかを探ります。役割の境界を越えて動く設計、カルチャーを日常的に言語化する仕組み、そして生成AI時代における柔軟な組織戦略──そのすべてにおいて、「今のフェーズに最適なあり方」を見極める視点が貫かれていました。
ニッチなニーズに挑む、Fintechスタートアップの現在地
まずは、RemitAid社の事業概要について教えてください。
私たちはクロスボーダー決済、特に法人間の国際送金を便利にするサービスを展開しています。現地口座の即時開設や送金のDXによって、従来の銀行を介した送金よりも80%以上手数料を削減できますし、煩雑な事務処理も圧倒的に軽減されます。
メインは「海外ラクヤス振込」というプロダクトで、特に不動産や産業機械、部品など、貿易の現場で高いニーズがあります。また、もう1つのプロダクトとしては、海外の展示会などで日本企業がその場でデジタル決済できる仕組みも提供していて、こちらはアートやジュエリー業界などが中心です。
複数のプロダクトを展開されているとのことですが、それぞれの市場での反応はいかがですか?
ありがたいことに、ニーズとソリューションがうまくマッチしていて、展示会向けのプロダクトは1年経たずに200社近くが利用するまでになりました。とはいえ利益率の課題もあり、今後の事業の柱は、やはり貿易の本流である「海外ラクヤス振込」の方になると考えています。

少数精鋭でもスケール可能──“構造化できる人材”の採用方針
現在のエンジニア組織の構成を教えてください。
正社員エンジニアは3名、副業・業務委託のメンバーが4名という体制です。採用チャネルはほぼリファラルとYOUTRUSTのみです。現在の正社員3名のうち2名はリファラル、1名はYOUTRUST経由です。
採用において重視しているポイントは何でしょうか?
技術スキルそのもの──たとえば「Goが書けるか」などは実はあまり見ていません。それよりも、「構造的に物事を捉え、設計に落とし込めるか」を重視しています。
面談では「この仕様を変えると、どの部分にどのような影響が及ぶと思いますか?」といった問いを投げて、因果関係をどう整理するかを見ることもありますね。表層的な技術的影響だけでなく、「運用や保守性にどう波及するか」「チーム全体の構造にどう関係するか」といった視点を持っているかを見ています。
スタートアップってピボットが当たり前の世界なので、今できる言語だけを見てフィットさせると後でアンマッチになる。だからこそ「再現性のある思考力」や、「変化に適応できる柔軟性」のほうが、よほど大事だと考えています。
全員がフルスタック。職能を越境するための設計思想
少人数のチームで、どのように役割分担されているのでしょうか?
私たちはフロントエンドやバックエンドといった分業はしておらず、要件定義、仕様設計、実装、テストまで、フルスタック・フルレイヤーで担当しています。つまり、技術だけでなくプロダクトマネジメントの領域まで踏み込んでいるんです。
職能の境界を設けずに進める中で、専門性の確保はどのように担保しているのでしょうか?
もちろん専門性が必要な場面もありますが、その場合は外部の業務委託メンバーやアドバイザーに助けてもらう体制を取っています。とはいえ、基本的な開発フローやプロダクトに関する意思決定は、すべて内製で回しています。
この体制を実現できている理由は?
メンバーに「タスク」ではなく「ミッション単位」で仕事を渡しているからです。「このAPIを作ってください」ではなく、「この顧客体験を実現するにはどうすればよいか?」という形で任せています。裁量と責任をセットで渡すことで、皆が考えて動ける状態が自然とできています。

“違い”を前提にする組織文化が、変化に強さをもたらす
少数精鋭の組織だと、価値観や考え方が似通いやすいと思いますが、意見の違いが出ることもあるのでしょうか?
かなりあります(笑)。私は「まず作って出す」タイプですが、他のメンバーは「堅牢性やセキュリティ重視」で、設計を固めてから動くタイプ。ですが、それぞれが強みを持っているので、プロダクトの性質やフェーズに応じて、どちらのアプローチがふさわしいかを毎回議論して決めています。
少人数のチームだからこそ、かえって空気を読んで意見を言いにくくなることもあるのでは?
まさにその通りです。だからこそ、私自身が率先して“反対意見”を言うようにしています。「あえて異論を出す」ことで、他の人も意見を出しやすくなるんじゃないかなって。以前も、ある仕様について議論が割れた際、全員が自分の立場を一度言語化した上で「そもそもなぜこれを作るのか」という原点に立ち返って整理し直したことがあります。
何よりも大事にしているのは、“納得感のある意思決定”です。そのためには、意見が違っても対話できる文化が欠かせません。
拾う、越境する、称賛する──RemitAid流カルチャー醸成の工夫
RemitAid社のカルチャーを象徴する行動があれば教えてください。
「落ちているボールを拾う」ですね。役割が明確に定義されていない仕事、面倒な仕様調整、誰かとのやりとり……そういった“誰もやりたくないけど必要なこと”を拾って動ける人がいるかどうかで、組織の前進速度がまったく変わってきます。
スタートアップって、構造や仕組みがまだ整っていない状態が当たり前なんですよね。だからこそ、拾える人がいるかどうかが本当に重要になる。言い換えれば、「拾う余地があること」自体が、スタートアップらしい組織の証でもあると思っています。
そういった「拾う」動きが、チームの中でどのように発展していくのかも気になります。
そうですね。あるメンバーは、拾った課題を私にパスする際に「この人にこう聞いておいてください」と、すべてお膳立てしてから渡してくれます。ボールを拾うだけでなく、“投げやすくしてくれる”動きが本当にありがたいです。
そういった行動が、実際にチーム内で称賛される場面もあるのでしょうか?
はい、週1回実施している『バリュー会』があります。弊社の行動指針に照らして、誰がどのような行動をしたかを具体的に共有し合う場です。
たとえば今のような“拾って動いた”行動が紹介されることも多く、それがなぜ価値ある判断だったのか、全体にどう貢献したのかまで、しっかり言語化して共有しています。
この“分解して言語化する”習慣によって、カルチャーが抽象論ではなく行動ベースで浸透していきます。「こういうときにこのバリューが活きるんだ」と、他のメンバーにも自然に伝わるんです。
また、毎朝『グッドアンドニュー』を共有する時間を設けています。ここでは、些細な気づきや良かったことを口にすることで、心理的な距離が縮まったり、相互理解が深まったりする感覚があります。形式ばらずに、自然な形で続けているのが良いのだと思います。
こうした取り組みが日常的にできるのも、今が少数精鋭のチームだからこそだと思っています。全員がカルチャーの担い手であり、それを言葉にして共有できる距離感がある。だからこそ制度ではなく、日々のちょっとした対話の積み重ねが何より大切なんですよね。

少数精鋭で最大の価値を出す──生成AI時代の組織設計論
今後の組織拡大について、どのように考えていますか?
正直、「何人まで増やす」といった採用計画は立てていません。むしろ、少人数でどれだけ大きなインパクトを出せるかを前提にしています。
生成AIの影響も大きそうですね。
はい。生成AIによってエンジニアの生産性は確実に上がっています。実際、海外では20名以下のチームで数百億円のバリュエーションを得ている例も出てきていて、これからは「人を増やせばスケールする」時代ではなくなると思います。
その中で、RemitAid社が目指す組織像とは?
役割の境界を越えて、全員が自律的に動き、補い合える組織です。そのためには、単に制度を整えるのではなく、「日常のコミュニケーション」や「思考の仕組み化」が鍵になると感じています。そうした設計を続けながら、変化に強く、しなやかな組織をつくっていきたいですね。

編集後記
RemitAid社の組織づくりには、「このフェーズ、この人数だからこそできることを最大化する」という視点が一貫していました。
全員がフルスタックで動き、裁量を持ってミッションに向き合う。そして、“落ちているボールを拾う”という姿勢が当たり前のように共有されています。そうした行動は週1回の「バリュー会」や日々の対話の中で称賛され、言語化されることで、組織全体に自然と浸透しているように感じました。
メンバー全員がカルチャーの担い手であるという前提があるからこそ、しなやかで強いチームが生まれているのだと思います。組織が大きくなる前だからこそ、カルチャーの型を自然と育てることができる──RemitAid社の取り組みには、そんな今だからこそできる組織づくりのヒントが詰まっていました。
自社の状況にあわせて、何を制度で整え、何を言葉で伝えるのか。そんな問いを立てるきっかけになれば嬉しいです。