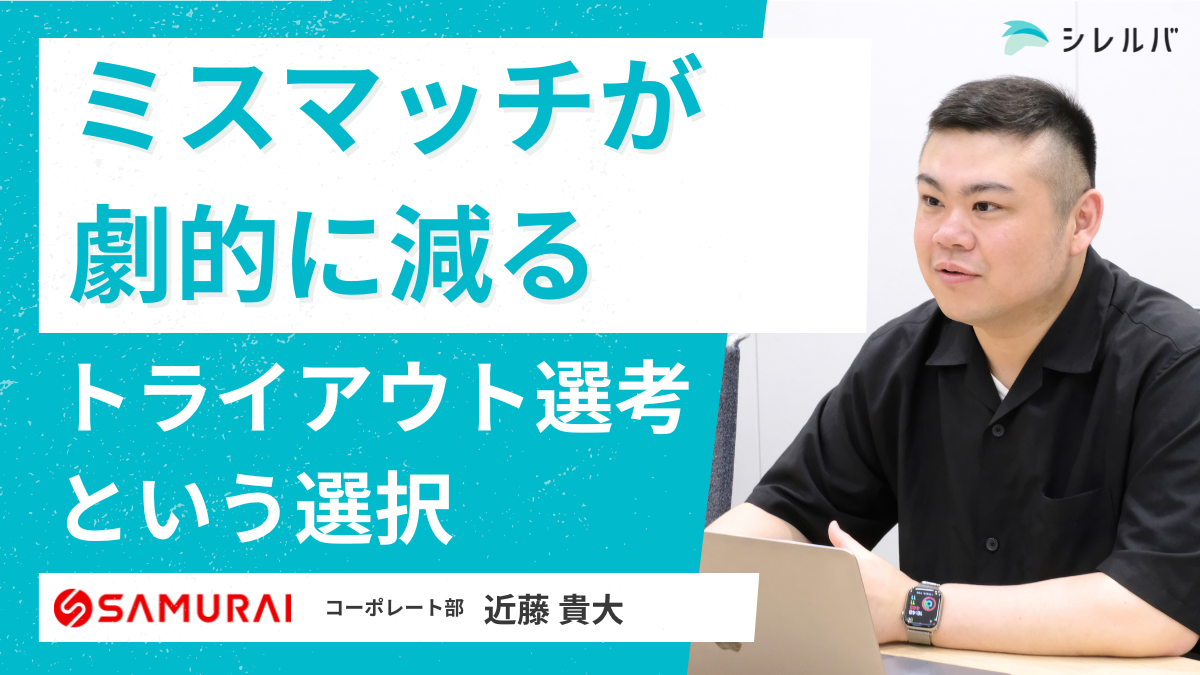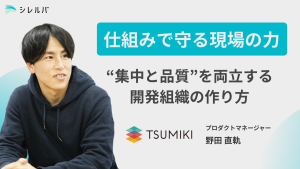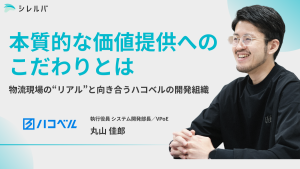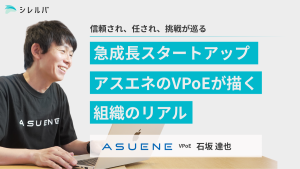株式会社SAMURAI
コーポレート部 人事担当
近藤 貴大
2025年6月現在は採用チームを統括し、ビジネス職からエンジニア採用まで幅広い領域の中途採用・新卒採用の立ち上げ、運用・採用マーケティングの推進・オペレーションの管理・広報チームの管理・GPTsなどを使用した業務効率化全般を担当。
プログラミングスクール『SAMURAI ENGINNER』をはじめ、IT教育からキャリア支援まで一気通貫のサービスを展開する株式会社SAMURAI。そんな同社で採用をリードするのが、近藤さんです。
教育に携わる企業として、採用もまた“人を育てる”視点で取り組んでいます。今回は、近藤さんに採用チーム立ち上げの苦労から、トライアウト制度を通じた独自の工夫、そして現場と一体で進める組織づくりまでお話を伺いました。
教育事業で培った“育成”の視点を採用へ
まず、SAMURAI社の事業概要について教えてください。
弊社は「SAMURAI ENGINNER」というプログラミングスクールを中心に、IT教育からキャリア支援まで一貫したサポートを行っている会社です。これまでに約4万5,000人の受講生を支援してきました。また、月額制で教材が学び放題の『SAMURAI TERAKOYA』というプラットフォームや、キャリア支援サービス『SAMURAI Career』を展開し、教育の入り口から出口までをカバーしています。
特徴的なのは、教育にとどまらず「学んだ後のキャリア」までを一気通貫でサポートしている点です。教育業界の中でも、ここまで横断的にサービスを展開している企業は少なく、エンジニアとしてのスキルだけでなく、その後のキャリア形成まで見据えた支援が可能です。
ゼロから採用体制を構築──奮闘の立ち上げ期
近藤さんが採用に関わり始めた当初の体制について教えてください。
私がジョインしたのは2022年4月です。当時はエンジニア採用活動の基盤も整っておらず、媒体は契約しているものの活用されていない、エージェントとのネットワークもない状態でした。もう何から手をつけていいのか分からず、まさにゼロからのスタートでした。
そこからどのように体制を立ち上げていったのでしょうか?
最初はとにかく一つひとつ試していくしかありませんでした。スカウト媒体の効果測定、スカウト文のトライアンドエラー、応募後の候補者対応、すべて一人で担っていました。最初の半年間はなかなかの激務でした(笑)。ただ、実際に試したからこそ見えてきた“自社に合う”手法があり、それが今に生きています。

“伝えていく”ことも採用のうち──発信の力
”自社に合う”手法があったとのことですが、具体的にどのような取り組みをされたのでしょうか?
一つは採用ブランディングです。採用は「ただ人を集める」というものではなく、「どんな組織をつくっていくか」を考える大切な営みだと思っています。ですので、情報発信を通じて私たちの価値観や雰囲気を伝えることは非常に重要です。特に、共感でつながる仲間を増やすには、日常の考え方や動きを、Wantedlyのストーリーなどを通して発信することが必須だと考えています。
Wantedlyでの発信では、どのような工夫をされていますか?
月3本の発信を継続する中で、デザイナーによるアイキャッチ画像の最適化をしました。当たり前ですが読んでもらうためには、まず“目に留まる”ことが大事なんですよね。アイキャッチ画像の最適化をし始めてから、80~100が平均と言われている中、弊社では倍近くのPVや最高で1000PVほどが取れるようになりました。結果として応募数にもつながっています。
「上下関係」ではなく「役割と責任」で動くチームに
記事の内容や企画のポイントはどこにありますか?
会社を知ってもらうためには、様々なテーマを発信することが大事だと考え、社員インタビュー、部署紹介、複数社員のクロストーク、1日密着記事などを作成しました。
他には社内の紹介だけにとどまらず、「教育業界全体に役立つテーマ」「チームの価値観やカルチャーが伝わる話」など、読んだ人に何かしら持ち帰ってもらえるような内容を心がけています。たとえば、AIを使った業務改善の話や、社内の総会レポートなど、実際の取り組みをわかりやすく紹介しています。

発信による効果はどう感じていますか?
Wantedly経由での応募は確実に増えており、記事を読んでから面談に来る方は、会社の雰囲気や価値観をある程度理解してくださっているので、面談もスムーズです。よりコアなお話に時間を使うことができるんですよね。また「あの記事を読んで共感しました」と言ってくださる方も多く、単なる採用広報を超えて、カルチャーに共感してくれる方々と出会うための大切なタッチポイントになっていると感じています。
今後も記事の本数だけでなく、質の向上を目指して、現場メンバーと連携しながら生の声をもっと届けていきたいと思っています。
“試してから始まる”採用──トライアウトという選択肢
他にも取り組みを聞ければと思いますが、選考フローで工夫されていることはありますか?
成長実感を得るには、自分で考えて行動する経験が必要だと思っています。
エンジニア採用の選考にはトライアウト期間を取り入れています。トライアウトは、候補者に副業として1~3か月間プロジェクトに関わっていただく制度です。稼働時間は週10時間ほどで、弊社がお願いしたい開発タスクに入っていただき、その中で技術力や進め方、チームとの相性などを見ていきます。タスクは候補者のスキルや志向に合わせてアサインし、レビューや相談体制も整えており、単なる業務テストではなく、一緒に働くための双方の“お試し期間”として機能しています。
導入のきっかけを教えてください。
以前、選考を通過して入社した方が、数日で退職されるという出来事がありました。候補者と会社側、それぞれに悪気はなくとも、面接だけではどうしても伝わらない価値観や期待値のズレが存在していた。その出来事が大きなきっかけとなり、双方にとって納得感のある選考方法を模索するなかで、このトライアウト制度を整備しました。
思い切った取り組みですね。実際に導入してみて、どんな変化がありましたか?
ミスマッチが劇的に減りました。以前は、面接で感じた印象と入社後のギャップが課題でしたが、トライアウト期間を経てお互いの理解が深まるので、納得感を持って入社いただけます。中にはトライアウトを通じて入社された方がMVPを取るような事例もあり、現場からの信頼も厚い制度です。評価も「開発力」だけでなく、「進め方」「周囲との連携」など、実務に近い観点で見られるので、入社後に期待と実際が大きくズレることが各段と減ります。
トライアウト中のフォロー体制についても教えてください。
週次で1on1を実施しており、業務内容のすり合わせやフィードバックを丁寧に行っています。エンジニア同士の相談や情報共有もSlack上で活発に行われており、候補者の方が安心して参加できるよう配慮しています。候補者からも「自分を知ってもらえている感覚がある」と言っていただけることが多く、結果的にオンボーディングも非常にスムーズです。
他社との違いを感じる点はどこですか?
多くの企業が選考を「見極める」場として設定しているのに対し、私たちのトライアウトは「一緒に働く準備期間」という考え方に近いです。「選ぶ・選ばれる」ではなく「一緒に働くために確認する」。このスタンスが、採用の場面だけでなく、その後の組織にも良い影響をもたらしていると感じています。

「採用」は組織を育てる土台づくり
今後のエンジニア採用の展望についてお聞かせください。
今後は、より現場主導の採用体制へと進化させていきたいと考えています。候補者にとって最もリアルな判断材料は、現場の人との会話です。ですので、選考フローの中で現場エンジニアが直接関与する比率をさらに増やしていく予定です。
また、初めての新卒採用にも挑戦中です。既に26卒向けに動き出しており、数名の内定も出ています。組織としては今後数年で社員数を増加させていく見込みです。
そうした進化を促す仕掛けとして、どんな取り組みが有効だと感じていますか?
一つは、Innovation Hubのような横断的な取り組みです。異なるスキルや背景を持つ人が交わり、お互いの知見を持ち寄る。そうした場が、組織全体に変化をもたらすきっかけになると考えています。
現場が採用に関わるようになって、どのような変化を感じていますか?
トライアウトや発信を通じて、入社前からチームとの接点が増えたことで、入社後のカルチャーフィットが非常にスムーズになりました。最近では、入社後すぐにプロダクト改善を提案し、実装までリードしてくれたメンバーもいます。
「採用活動は入社したら終わりではない」という意識が、チーム全体に少しずつ浸透してきている実感があります。これからも、入社後の活躍まで見据えた採用を、現場と一緒に育てていきたいと思います。

編集後記
「採用は、人を“選ぶ”場ではなく、一緒に働く仲間を“育てる”入り口」。取材を通して近藤さんが何度も繰り返されていた言葉が、とても印象的でした。
トライアウトや情報発信、そして現場を巻き込んだ採用体制。どれもが単なる採用手法ではなく、組織として“育てる文化”を根付かせるための手段であり、その一つひとつに丁寧な意図が込められていると感じます。
候補者がどんな人かを見極めるのと同じくらい、「自分たちはどういう組織なのか」を伝えることを大切にしているSAMURAIの採用の在り方は、これからの時代のひとつのモデルなのかもしれません。