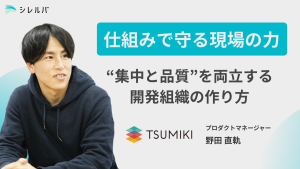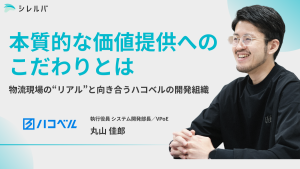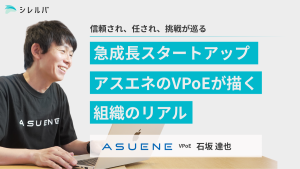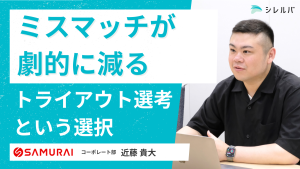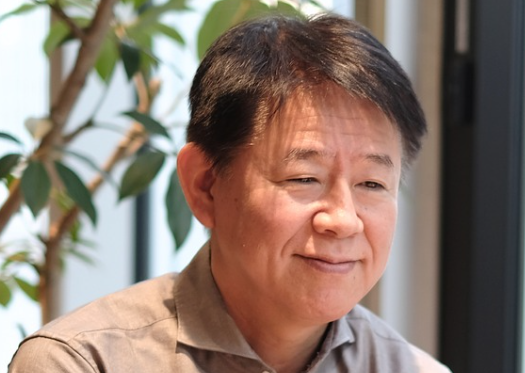
KINTOテクノロジーズ株式会社
取締役副社長
景山 均
楽天にて、楽天グループのデータセンター・ネットワーク・サーバーなどのインフラや、ID サービス・スーパーポイントサービス・メールサービス・マーケティング DWH・ネットスーパー・電子マネー・物流システムなどの開発を統括。その後、ニトリの IT、物流システムの責任者を経て、2019年6月にトヨタファイナンシャルサービスに入社。デジタル IT 部隊の立ち上げをゼロから実施。2021年4月より現職。
トヨタグループの内製開発部隊として2021年に設立されたKINTOテクノロジーズ。設立からわずか数年でエンジニア組織は370名を超える規模へと急拡大し、そのうち9割以上が技術職という圧倒的な「内製志向」を実現しています。なぜそこまで内製にこだわるのか? 組織の立ち上げ期にどんな苦労があったのか?
本記事では副社長の景山さんに、内製化に込めた想いや組織の成長戦略、カルチャー浸透の工夫など、内製組織づくりの裏側を伺いました。
内製でなければ、コンシューマーサービスは育たない
まずはじめに、KINTOテクノロジーズ社の事業内容について教えてください。
KINTOテクノロジーズは、トヨタグループにおけるモビリティサービス開発の中核を担うテックカンパニーです。主にKINTOブランドの新車・中古車サブスクリプションをはじめとしたWebサービスやアプリの開発・運用を担当しており、それに関連する業務支援ツール、販売店向けシステム、共通プラットフォームなども一貫して内製で手がけています。KINTOだけでなく、トヨタ自動車や販売会社と連携した領域まで含めて、非常に幅広い開発を行っているのが特徴です。
KINTOテクノロジーズ社設立の背景を教えてください。
トヨタグループ内で、コンシューマー向けのWebサービスやアプリを自社で開発できる体制を作る必要がある、というところから構想がスタートしました。製造業では“手の内化”の思想が根付いていますが、それをデジタルサービスの領域でも実現したいという考えでした。
最初はどのような体制から始まったのですか?
私が入社したのは2019年で、その時点ではエンジニアが私ひとりという状態でした。そこから少しずつ採用を進め、2021年に正式にKINTOテクノロジーズが設立されました。現在ではエンジニアが300名を超えていて、バックエンド、フロントエンド、モバイル、インフラ、QA、デザイナーまで、必要なポジションはすべて揃っています。
すべてのサービスを内製で開発されているのですね。
はい、開発はすべて内製です。プロダクトもKINTOのカーサブスクリプション、販売店向けシステム、社内の業務支援システム、モバイルアプリ、ID・決済など多岐にわたります。私たちは“コンシューマー向け”のビジネスをしている以上、リリースして終わりではなく、反応を見ながら改善していく必要があります。そのためには、開発を自社で抱え、スピードと柔軟性を確保しておく必要があると考えています。

拡大フェーズに生じたカルチャーギャップとその突破口
急拡大の中で、組織課題はありましたか?
最も大きな課題は、カルチャーの不在でした。立ち上げ当初は、内製開発に関する共通の価値観が組織内に存在していませんでした。採用もスキル重視で進めていたため、仕事の進め方や意思決定の考え方にだんだんズレが出てきました。特に、Webサービス特有の仮説検証サイクルや、顧客視点での開発思想を浸透させるのに苦労しました。
事業側や他部署との間にもギャップがあったのでしょうか?
ありました。特に、要件を決めてベンダーに発注するやり方が当然だと考えていた方々からは、「なぜすべて内製化する必要があるのか?」という声も正直ありました。それまでの開発スタイルでは、業務要件を整理して、外部のベンダーに実装を委ねるという進め方が主流だったのだと思います。
でも、私たちが目指しているのは、あらかじめ決まった仕様をただ形にするような開発ではありません。ユーザーの反応を見ながら、何が本当に価値につながるのかを探し続けていくような、変化を前提とした開発です。
こうした考えの違いもあったため、当然ながら社内でも開発に対する認識のズレやカルチャーのギャップが生まれてしまいました。
どうやってそのカルチャーギャップを乗り越えたのですか?
とにかく対話です。なぜ私たちが内製にこだわるのか、なぜプロダクト起点で考えるべきなのか、根気強く説明を繰り返しました。
また、現場でしっかり成果を出していくことで、内製の価値を体感として理解してもらう努力もしました。「なぜ作るのか」「なぜ今なのか」といった背景を共有するプロセスを意識的に増やしたことで、少しずつ共感が広がっていったと思います。
「ノウハウは現場に宿る」からこその内製主義
改めて、内製化の最大の価値は何だとお考えですか?
やはり、ノウハウが社内に蓄積されていくことだと思います。プロダクトに関する知見は、開発に関わるエンジニアの手元に自然とたまっていきます。お客様の反応を受けて、すぐに改善に活かせる。そのサイクルを繰り返すことで、プロダクトが磨かれていきます。
ベンダーではその蓄積が難しいのでしょうか?
そうですね。ベンダーに発注する開発の場合、リリースが終わると担当者が変わったり、他の案件に移ったりしてしまいます。すると仕様の背景や技術的な判断理由も失われがちです。継続的な改善が前提のサービスでは、それが大きなハンデになります。
内製なら、リリース後も同じメンバーが責任を持ってプロダクトを育て続けることができますよね。

“安くて高品質”ではなく、“柔軟で速い”を選ぶ
コスト面での議論もあったのではないですか?
ありました。やはり「外注した方がコストを抑えられるのでは?」という意見はありましたし、実際にそう感じる場面もあると思います。ただ、コストだけで判断してしまうと、柔軟性やスピードといった価値を見落としてしまいます。
具体的には、どのような違いがありますか?
たとえば、ベンダーにお願いしていたら、バグ対応ひとつとっても契約範囲や責任分解の調整から入りますよね。でも内製であれば、バグが出たその日のうちに原因を特定し、即座に修正できます。これは事業にとって非常に大きな差です。
品質管理の考え方も違いそうですね。
まさにそこが違いです。私たちは“過剰品質”を避けるようにしています。Webサービスの場合、改善前提なので“とりあえず出してみて、反応を見る”というスタイルがフィットします。高い品質を目指すより、柔軟に直せる構造を重視しています。
結果として、必要最小限のテストと高いリリース頻度のバランスを取りながら、品質とスピードの最適解を追求できるのです。
マネジメント=昇進ではない。エンジニアを主役にする評価制度
急拡大に際して、組織課題はありましたか?
はい。特に2022年ごろは急拡大のタイミングで、プレイングマネージャーが20人近いメンバーを見る状態になっていました。当然ながら、個別のケアや育成までは手が回らず、メンバーからも「誰に相談していいか分からない」という声が上がってきました。
どのように改善していったのでしょうか?
まずは組織を小分けにし、専任のピープルマネージャーを増やしました。同時に、評価制度も見直しました。マネージャーにならなければ昇給できないような構造をやめて、技術に専念した人も正当に評価されるようにしています。
エンジニアが主役でいられる仕組みを整えたのですね。
はい。むしろ、マネージャーよりもエンジニアの方が報酬が高いケースもあります。評価軸を役職ではなく成果に置くことで、キャリアの選択肢も広がり、自律的に成長していける組織になってきたと感じています。マネジメントは「キャリアアップ」ではなく「役割」として捉えることで、無理に昇進させるような状況もなくなりました。
こうした評価制度の整備と同時に、組織そのもののあり方も見直してきました。
特定の形に固執せず、状況に応じて組織の構造そのものを柔軟に変えていくことが、強い組織づくりには欠かせないと考えています。

組織の形も“変化前提”。3カ月単位で再編成する理由
組織のあり方についても、状況に応じて柔軟に変えていると伺いました。具体的には、どのように組織体制を見直しているのでしょうか?
理由は明確で、組織が安定しすぎると閉じてしまうからです。特定のマネージャーのもとに同じような人ばかり集まり、そこから外に出にくくなる。そうなると、新しい視点や変化を受け入れられなくなってしまうんです。
それで3カ月に一度、組織を見直しているのですね。
はい。プロダクトの状況や人の動きを見て、最適な配置に変え続けています。理想の組織像を追い求めるのではなく、今いる人で最適をつくる。その積み重ねが、組織の柔軟性と強さにつながっていると考えています。ある種の“組織的アジャイル開発”と言ってもよいかもしれません。
カルチャーを“しつこく”伝える。トップの責任としての浸透活動
景山さんご自身が、入社者向けのオリエンテーションを担当されていると聞きました。
はい。毎月、全入社者に対して45分ほどお話ししています。「なぜこの組織が存在しているのか」「どんな価値観を大切にしているのか」といった背景を伝えるようにしています。
トップが直接語る意義は大きそうですね。
とても大事だと思っています。以前、700人規模の組織でマネージャー経由で伝達していたとき、何も伝わらなかった経験があったんですよね。だから今は、フラットな構造と直接の対話を大切にしています。
指示の「背景」や「意図」を言葉にすることで、現場の判断精度も上がりますし、結果として自律的な組織づくりにつながっていると実感しています。
これまでの組織づくりを振り返って、どのように感じていますか?
自分たちのスタイルや文化を模索しながらの4年間でしたが、「今いるメンバーで最適をつくる」という姿勢は変わっていないと思います。正解のない中で、都度チューニングしながら進んできました。
特に、過去に自分が失敗した経験や、うまくいかなかった組織運営の記憶が、今の判断軸になっています。「こうすると人が育たなかった」「こういう伝え方は響かなかった」といった記憶があるからこそ、組織の構造やコミュニケーションに対して慎重でありたいと思っています。
今後、どのような組織を目指していきたいと考えていますか?
引き続き、技術者が主役でいられる組織にしたいです。意思決定の透明性を保ち、カルチャーを丁寧に伝えながら、信頼の中で自律的に動ける環境を作っていきたい。組織が大きくなるほど、意図しない文化が生まれるリスクも高まるので、トップが繰り返し言葉にして伝えることの重要性はこれからも変わりません。
今はまだ発展途上ですが、「ここにいると成長できる」と思ってもらえる組織でありたいですね。

編集後記
変化に強く、そして変化を恐れない組織をつくるために──。KINTOテクノロジーズの組織づくりは、“理想の構造”を求めるのではなく、「今ここにいる人と向き合いながら、最適をつくる」ことを徹底していました。
変化の激しいWebサービス開発の現場で戦うには、組織もまた柔軟に変化し続けなければなりません。そしてそれを支えるのが、現場を信じ、価値観を言葉にして伝え続けるリーダーの姿勢です
370人を超える組織においても、エンジニアが主役でいられる。それがKINTOテクノロジーズの最大の強みであり、内製組織が持つ本質的な価値なのだと感じました。